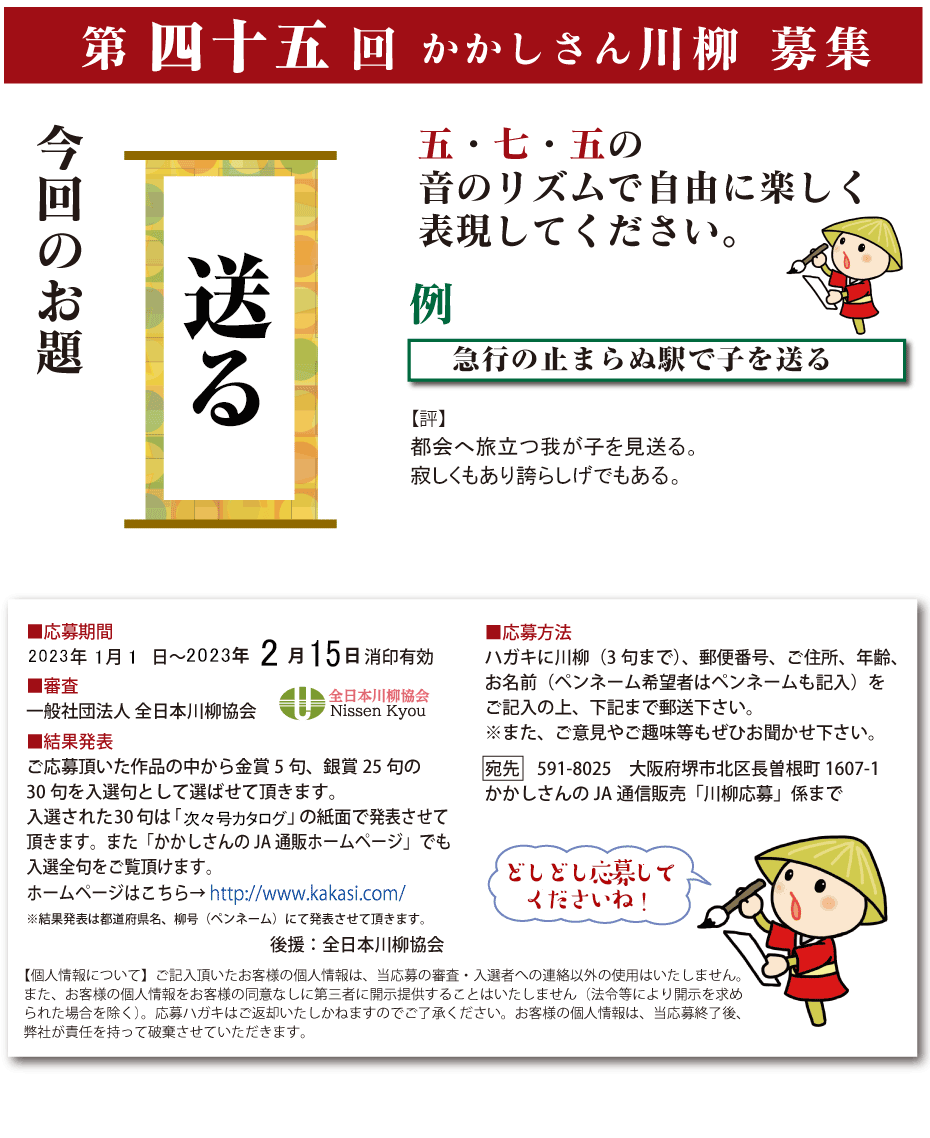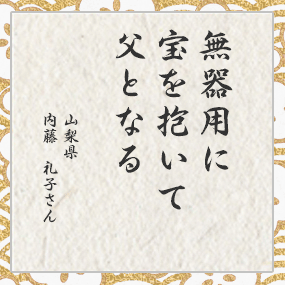
我が子という宝を抱いて初めて自覚した父という字の重いこと。
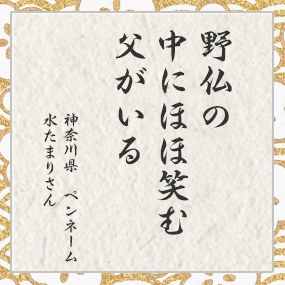
少し耳は欠けたが目じりの下がった父が野におわす。豊作を共に喜ぶ野仏の父。
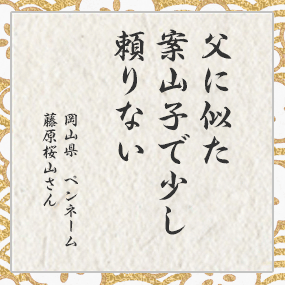
イノシシやカラスにちょっとあなどられ。それでも眉は一文字。どこか父似の案山子。
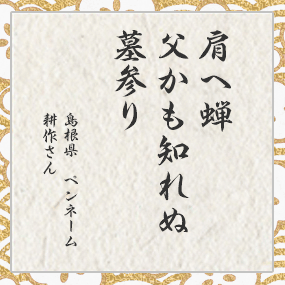
久方ぶりの墓参り。無沙汰を詫びたその肩に止まった蝉はきっと。
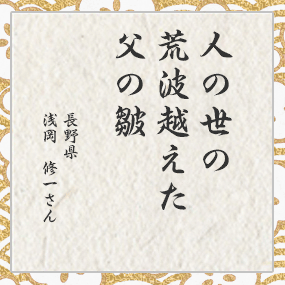
父の横顔を氷河が刻む。その一本を刻ませたのはまさしく私。
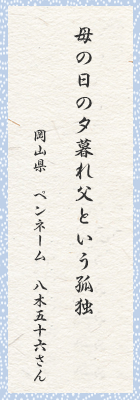
父の日は母の日ほど世間も家族も騒いでくれぬ、と一人ぶつぶつ。夕日に長い父の影。
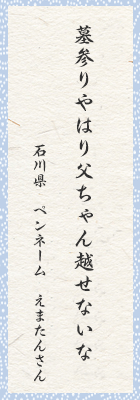
これまでの来し方を父に報告。色々あったけとやはり父ちゃんには勝てないな。
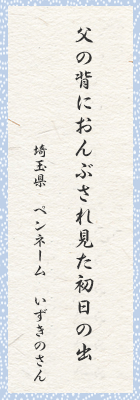
一年の始まりを父の背で。あれからの歳月。今は我が子に父がしたように。
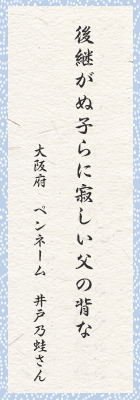
継いでくれる子があるからこの手もこの足も。この頃しびれや踏ん張りがきかぬ足となった。

八十八の手間が要る米作り。みんな父の背中が教えてくれた。

祖国ということばがふとよみがえる終戦日。父の死を決して犬死にさせてはならぬと思う日々。
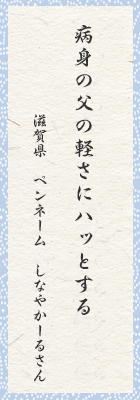
岩だと思った父がこんなに軽いとは。つくづくと歳月は残酷なものよ。
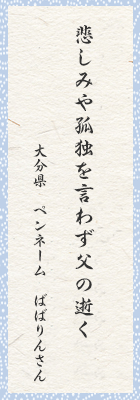
俗にいう。「痩せても枯れても」。志しの高い父だった。
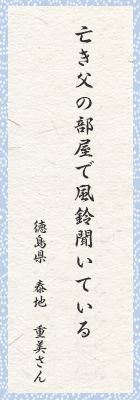
こよなく愛した南部風鈴。あるかなしかの風を掴んで澄み渡る響きを。

私が歩けば月も歩く。心配性な父という月。木陰に隠れ屋並みに隠れひょいと顔を出す。

父という存在は遺影でしか。若き父に両手を合わせ八十年。

あっ、父がこんなところで生きている。つくづく父の子でよかったと思う一日。
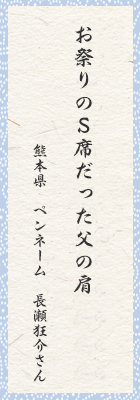
サーカスも猿廻しも。祭りの最後の打ち上げ花火も。父の肩は最高の特等席。
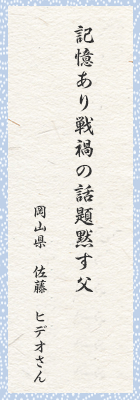
もうあの戦争に触れたくない。人が人でなくなる戦争。黙すのみ。
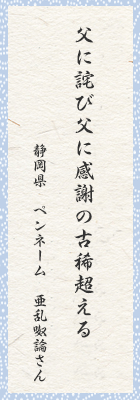
既にもう父の年齢を超えた。あの時ありがとうのひと言を言えなかったことを悔やむ。
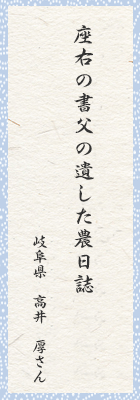
浸けた種もみが水の中で息をする。刈り取りはいつ。季節の中で農日誌をまためくる。

納屋の隅で父の鍬が出番を待っている。まさに土に生き生かされた父。
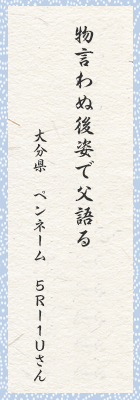
この広い岩のごとき後姿はときに饒舌。進むべき道を問うてみる。

怖かった。でも夜のしじまに低く響くあの声は。宮の杜の主そのもの。

あの時に聞いておけばよかったということが十指に余る。やっぱり父は岩だった。

山だった父の背広が今この私の肩に。歳月をこんな形で知るなんて。

家族思いの父。眉間のシワを知っていたのは誰でもない。かんな屑。

鍬の柄が父の形で少しくぼんでいるのは気のせいか。確かに残る父の体温。
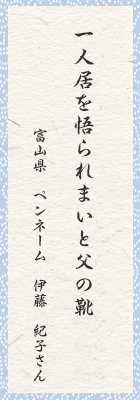
玄関に小舟のような父の靴一足。女一人を悟られまいと父を借りる。

「何になりたい」と父に問われたのはまだ肩ぐるまの頃。今、自分がここにいるのはあの日が起点。