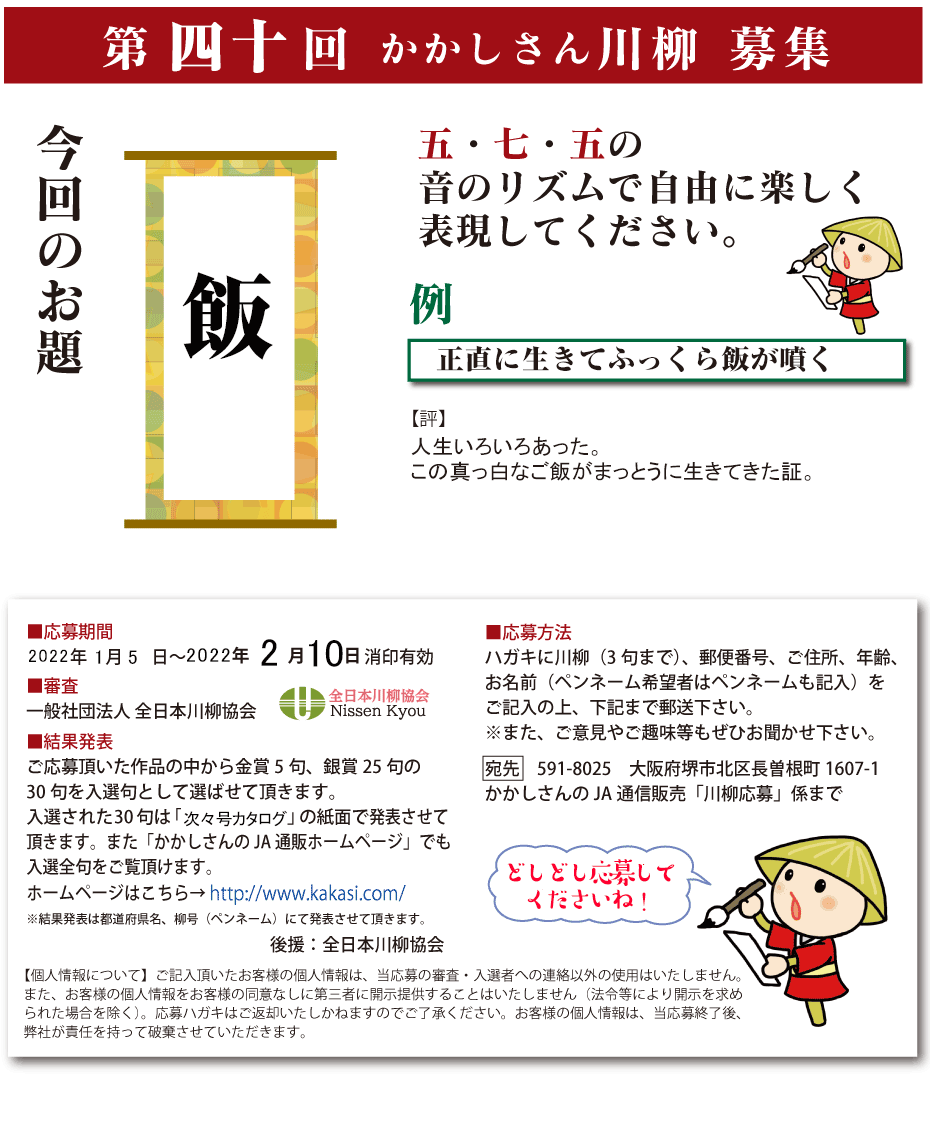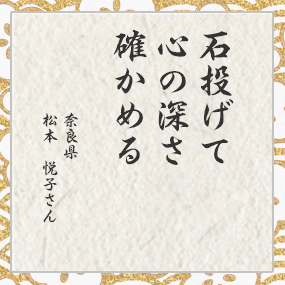
石投げて井戸の深さを確かめる。人の心はまるで井戸。深かったり浅かったり。
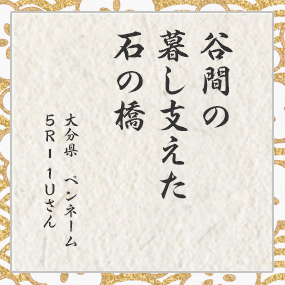
この小さな石の橋を人も社会もそして文化も渡ってきた。谷間の暮しを知っている石の橋。
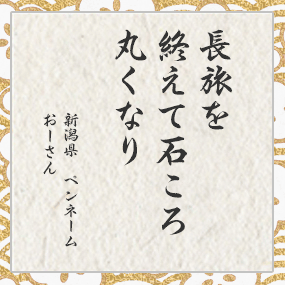
流される度にあちこちの角が取れ平均値化してしまった川底の石たち。
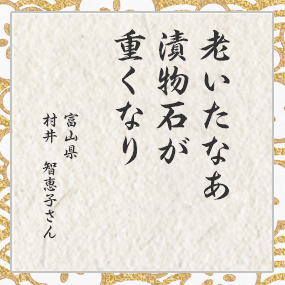
ひょいと持ち上げていたこの漬物石。その石が重い。歳月というものはつくづく残酷。
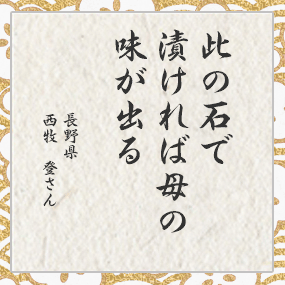
母の手順で青菜を漬ける。最後はこの重石。きっと母が見守ってくれることだろう。
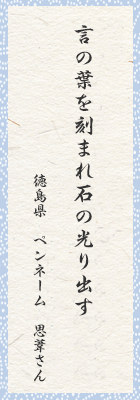
何の変哲もない石も言葉を刻めばだんだんと宿る魂。
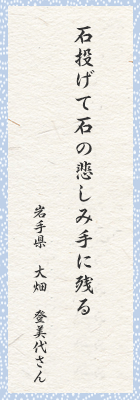
投げてはみたものの手に残るこの空虚さは何だろう。投げられた石に傷つく人がいる限り。

喜びも哀しみもみんな受け止めてくりる母の里。まるで水の輪が広がるように。
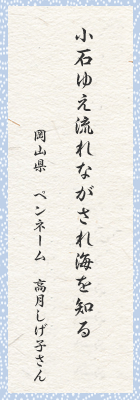
岩はでんとして大会を知らない。その点小石は身軽。社会という大海を知った驚き。
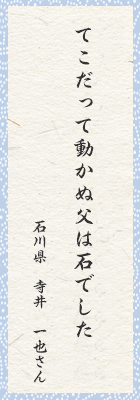
石部金吉とはこのことか。一徹を貫き主義を通した父だった。

光るものなんてこの節くれの指には似合わない。この節くれこそが光るもの。
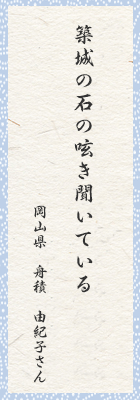
人は石垣人は城、だという。石に耳を当てると確かに歓声や嘆きの声が。

振り返る人生に悔いなどは。力いっぱい生きてきた。生まれた時のように終章も。

納屋の隅にごろんと転がるつけもの石。祖母から母、そして私。一子相伝のつけものの味。

口に出すこともはばかれるほどの敗戦後の暮し。「石を齧る」という厳しささえ生易しいほどに。
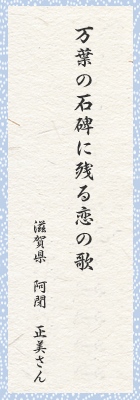
古人のことばの何という床しさ。野の花、鳥の声に託した恋の歌。

用心深いということは必要なことではあるが橋を渡れぬままに終わる人生も。
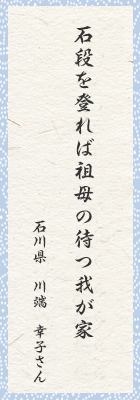
一段ずつ、一段ずつ祖母に近ずく石段。何年ぶりだろう。一気に駆け上がりたい衝動も。
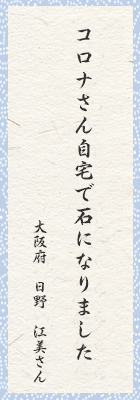
自粛は人をこれほどまでに退化させるのか。人は人によって磨かれるというのに。

二人の心を確かめあった寺の旅。石畳の感触を未だこの足の裏が知っている。
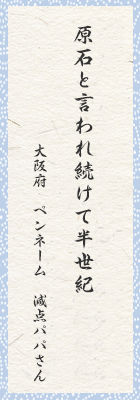
一流といわれるのはほんの一握り。村のスーパースターも二軍の練習場で打ち込みの毎日。

何と懐かしい昭和の風景。今はもう蹴る石さえも見つからぬ。ああ、文明とは。
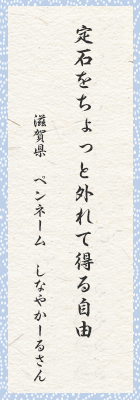
決まった時間、決まった道の味気無さ。道草は人生を豊かにしてくれる。

あれから76年。若き兵士たちの祖国愛がひしひし。刻まれた兵の名をなぞる指先の痛み。
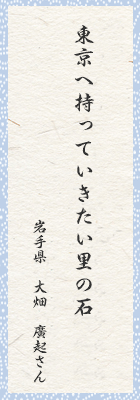
行き交う人は速足で無表情。そんな時たっぷりと太陽を浴びた里の石に体を預けたい。
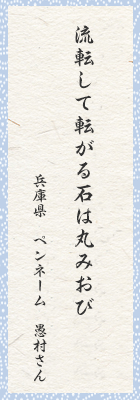
昨日は東今日は西。雨風に打たれて人の情けをようやく知った好々爺。

世の中を根底から変えた新型コロナ。私たちを見守る石仏さんもどうぞ御身大切に。
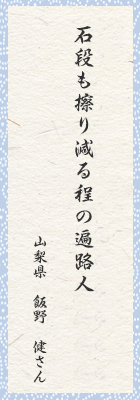
人はみな悩むために生まれてきたのかと思うほどの人の列。その人らを確と受け止めている石段。
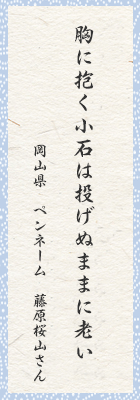
その一歩を踏み切れなかった小心を嘆くまい。それはそれで小さいながらも幸を得た今。

姉も弟も県境を越えることはできなかった「コロナ盆」。こうして兄妹の分も墓石を洗い清める。