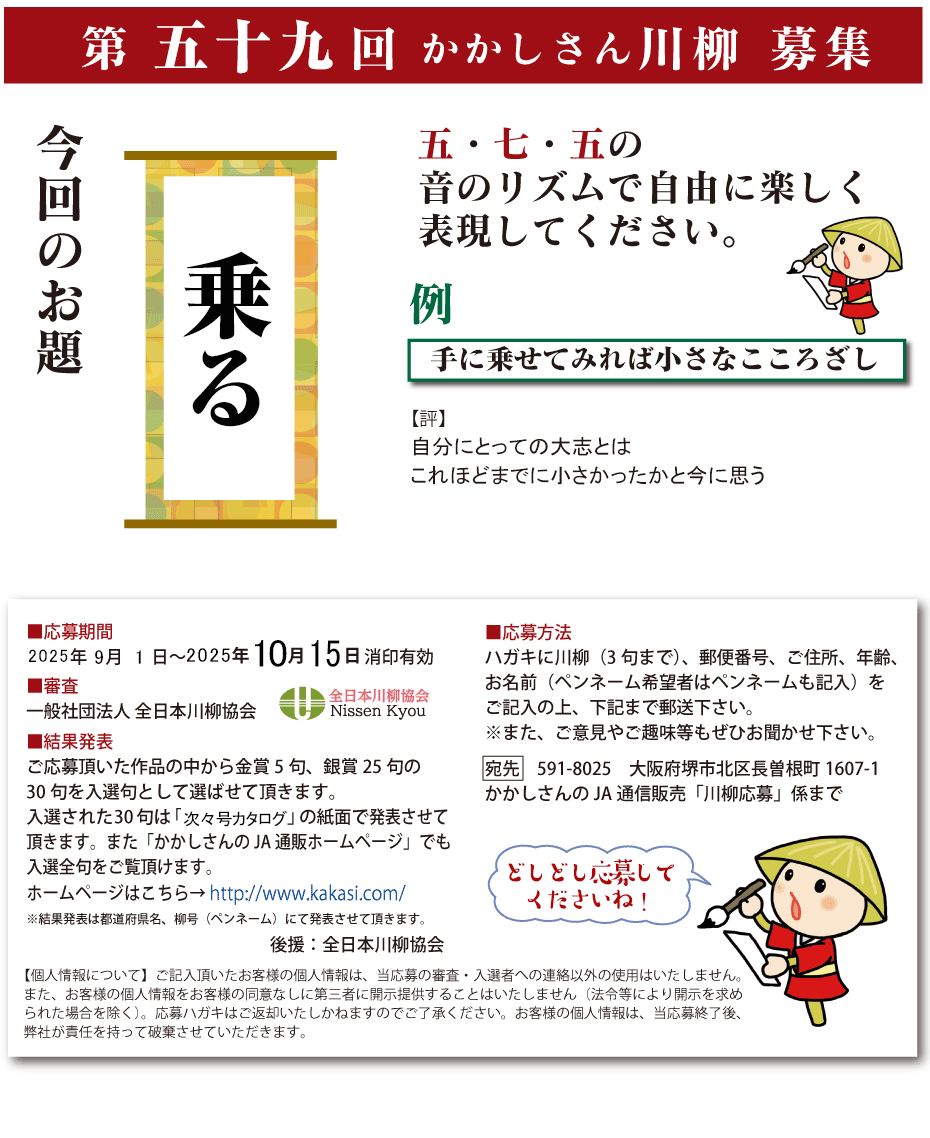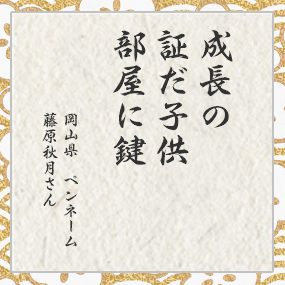
子どもから大人への階段。誰からも干渉されたくないという自意識もその一歩。
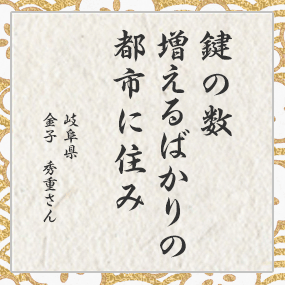
人間不信の数と鍵の数が同じとは。田舎では鍵など持ったこともないのに。
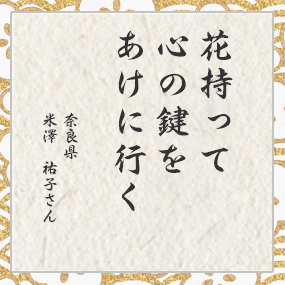
頑なな心の鍵を開けるにはどんな優しいことばより、季節の花が有効と教えてくれた春の風。
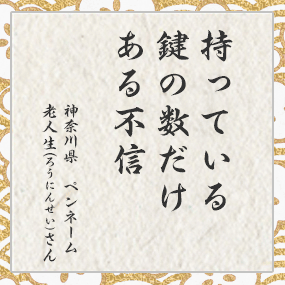
この鍵だけが信じられる存在とは何たる不幸。それも一つふたつと増えて。
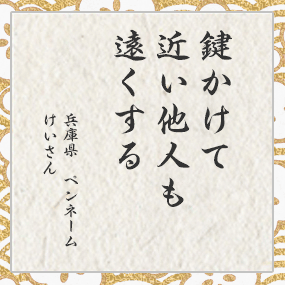
この心の内は誰にも話せぬそして覗かせぬ。かくして一人去りふたり去り。
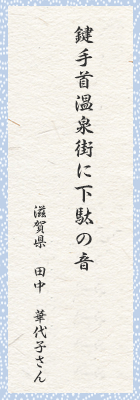
この光景はまさしく昭和の景。解放の温泉街にきて手首に縛られる鍵がまたジョーク。

未練とはそういうもの。そしてまた合鍵を持つ二人の物語。

生臭きものもシャリシャリにしてしまう歳月というものは。かくして秘密の蔵も。
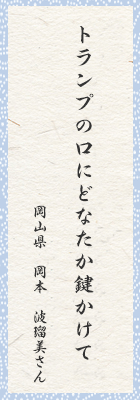
この人の正と邪、善と悪、そして美と醜などの区別は入り乱れて。

ひたすらひたすら北からの便りを待っている拉致家族。時はいつでも容赦なく。

赤ちゃんを真ん中にして大人たち。損得がいかに貧しいかをこの笑顔が教える。

住んでいるこの世界が全ての世界とガザの子ら。鍵穴から見える世界はおとぎの世界か。

お天道さまの下で恥じぬ暮らしには、鍵の一つもあればいい。

この鍵穴から果たして明日が見えるのだろうか。今日を精一杯生きてこその明日が。
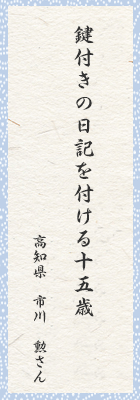
この私の気持ちなど誰も分かってはくれない。自分の世界が全ての十五歳。
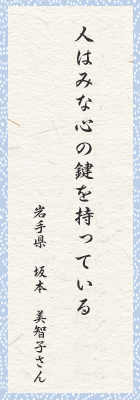
この私の心には誰も踏み込むことなどはできない。私の心は私だけの逃げ場所でもある。

二人だけの世界を確保してくれる観覧車。指さす夜景も祝福してくれる。

これからは誰にも頼らず一人の力で。カツカツとビルにこだまするヒールの音も小気味よく。
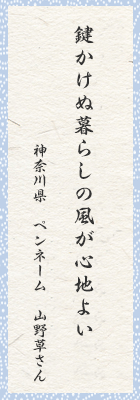
信じるということがこれほど心地よいとは。暮らしに慣れて風も背を押す。
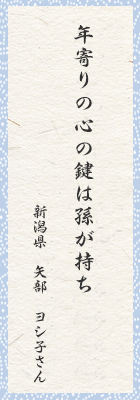
子はかすがいも、寿命が延びた現在は時に子から孫へと移行しても何の不思議もない。
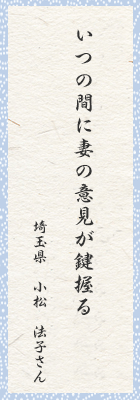
悔しいけれどいつの間にか妻に握られていた主導権。この手に戻るのはいつの日か。

親の目の届かぬ子らにも社会の温かい風は吹いてくる。未来はこの子らの肩に。

たとえ夫婦といえど踏み込めぬそれぞれの部屋を持つことはとても大切。

年々無力化していく国連。このところ大国といわれる国の専横が目に余る。
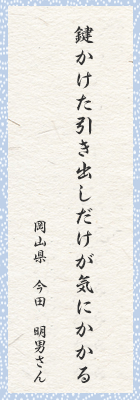
今思えば鍵などかけなければよかった。青天の下、恥ずべきことは何もないのに。
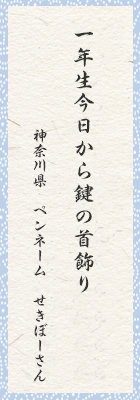
初めて親の腕から抜けた一年生。首には鍵がきらりと無事の帰りを待つ家が。
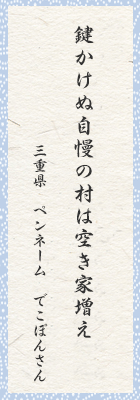
のんびりと誰もが顔見知りの村の屋根瓦。いつしか子らの声も途絶えて久し。

人を信じることの素晴らしさを教えてくれた相方。生涯の伴侶へ歩を揃えて。
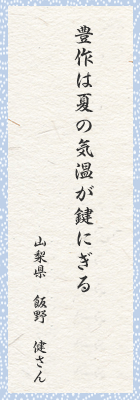
田水沸く、と言われた夏がいまでは沸騰。過ぎたるは何とやら。これも人の仕業か。

こうなれば連れ合いに何もかも腹蔵なくの老いの道。時に叱られ時に褒められ。