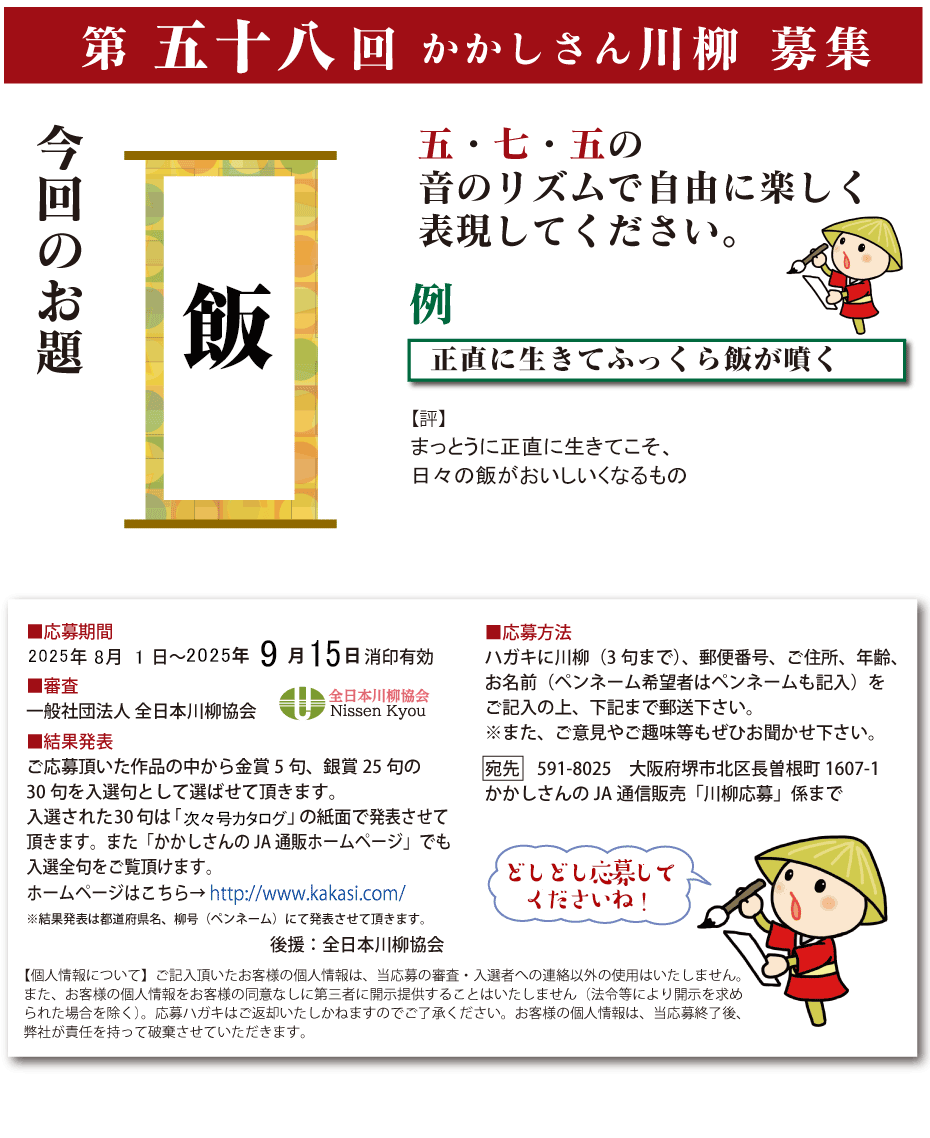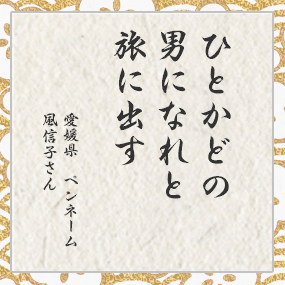
他人の飯を食ってこい。というのも男として、父としての武骨な愛の表現であろう。
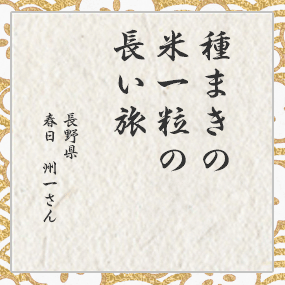
収穫まで八十八の角を曲がればならぬ。雪解け水に浸す種籾の鼓動がかすかにこの手に。
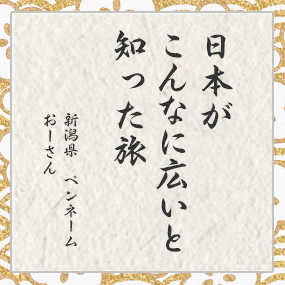
まるで井の中の何とやら。そこから見える空が全てだと思っていた。言葉も食べるものも新鮮な驚き。
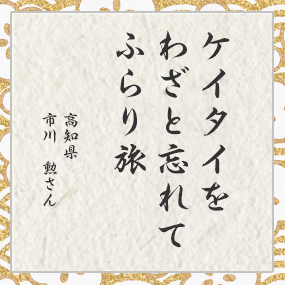
考えてみればケイタイに縛られていた一日24時間。このケイタイというくさりを断ち切って。
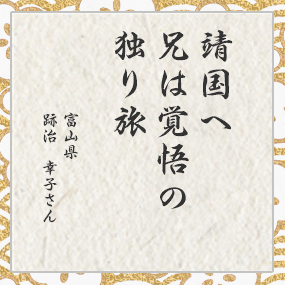
そういえば「東京だよおっ母さん」の兄さんもここに。だが戦争はもう二度と。
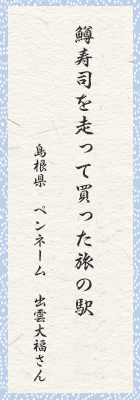
旅行ガイドで知った名物の駅弁。手渡してくれた店員の訛が温かい。
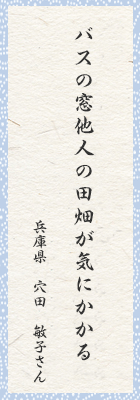
これもまた職業病の一つと言えるのであろうか。自分の稲田とついつい比較してしまうバスの窓。

この落暉の赤を、夜空の月を見ながら残してきた人のことなどを。
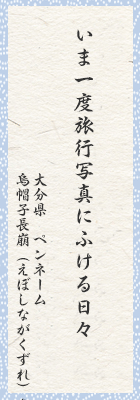
弾けた日々だった。見るもの、聞くもの、食べるもの。旅行写真は饒舌に語る。

歳月は時に残酷に一面を持ち合わす。こうしてまでもの旅の魅力とは。
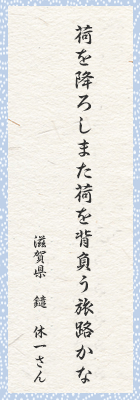
人生の旅とはこんなもの。それでも旅の荷は重いほど生きがいを連れてくる。
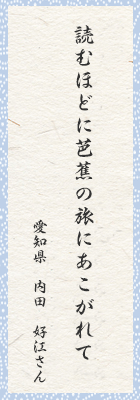
過ぎゆく月日も旅人と自身を重ねた芭蕉。夏草、蝉など小さな命にも心を寄せた芭蕉の旅にあこがれて。
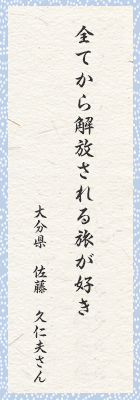
考えてみればしがらみの中に生きてきたこれまでの来し方。旅というものはそれらを忘れさせてくれる。

異国の土になった父を訪ねる悔恨の旅。二度と戦争は、の誓いを胸に。
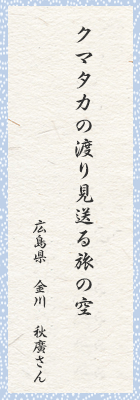
人に道や鉄道があるようにクマタカにも移動する道や駅があることを知った旅の空。
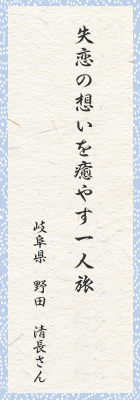
胸の痛みを空と海の青に溶かせば少しは元に戻れるだろうか。やっぱり日にち薬に頼るしかないのか。
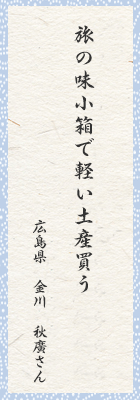
どんな小さなものでも大きな感謝の気持ちさえあれば相手に思いは通じよう。
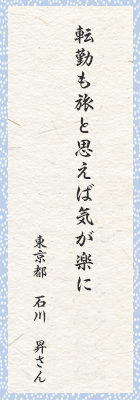
異郷には異郷の良さがきっと。だっていつかの旅がそうだった。
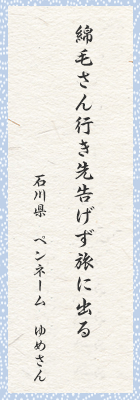
風に身を任せてタンポポは。ふわりと見知らぬ地に降りて。新しい出会いを待っている。

どこかに大切なものがきっとある筈と小さな荷と杖を頼りの遍路道。あれ、私に似た人があそこにも。
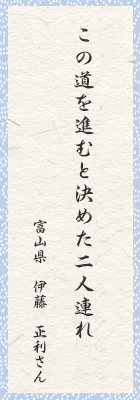
覚悟を決めたリンゴ箱の家具からの出発。これを食卓にして向かい合った四畳半。
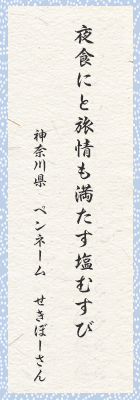
振り返る昭和。母の手の温もりが塩むすびにまだ残る。

あのか弱い翅でこの海原を渡るのか。この蝶にとって生きるとは海を渡ること。
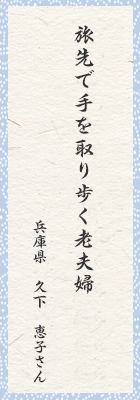
お互いを杖として。振り返る道は遠くかすむが行く先のどこかでこの手を放すかも。
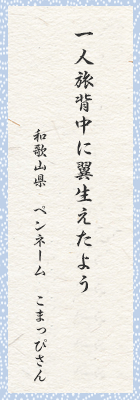
がんじがらめの昨日までを脱ぎ捨て今日からは。一人の旅がこれほど楽しいものだとは。

傷心を優しく包み込むリルケの言葉たち。言葉にも心を包むガーゼがあるなんて。
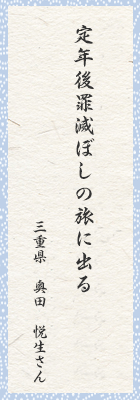
考えてみればわき目も振らぬ馬車馬のような勤め人だった。せめて定年後の一日は妻に上げ膳の旅を。

へえー、こんな連れ合いだったとは。旅は新しい発見の道行きでもある。
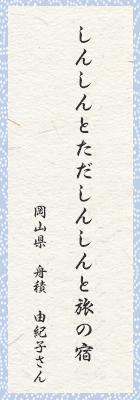
耳を澄ませば雪の降る音がかすかに。「しんしん」のオノマトペの遣い方に脱帽。
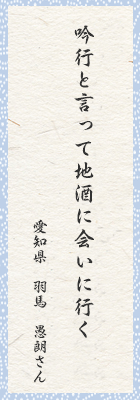
単なる酒飲みが文化の名を借りて。この面白き振る舞いがまた文化、ともいうべきか。