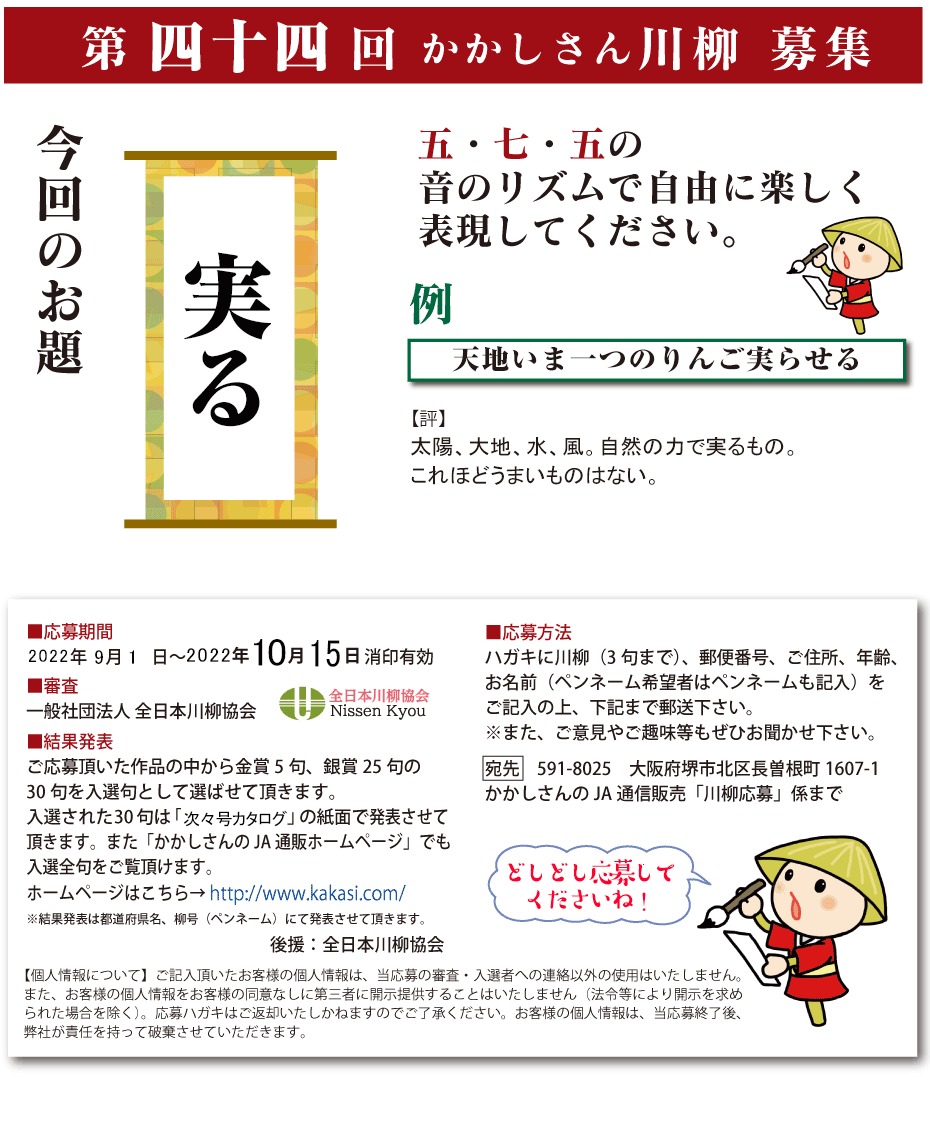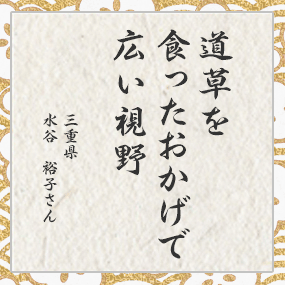
教科書に書いていない道を歩いた。お陰で人の温みや痛みを知った。
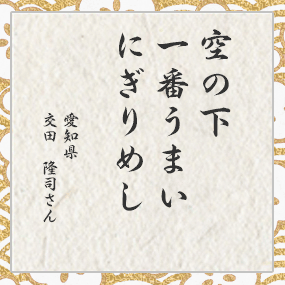
握り飯が旨いのは握った人の体温があるから。指にくっ付いためし粒の一つひとつにも。
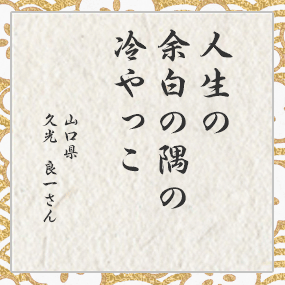
余白にあって存在感の冷やっこ。刻んだネギの青と冷たい白のコントラストが何とも。
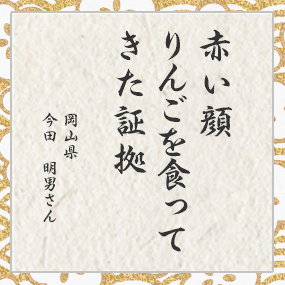
バナナを食べても黄色くならない顔がりんごを食べたら。この見つけが秀逸。
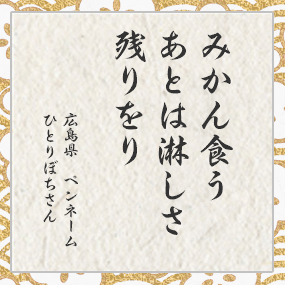
何か無心に目の前のみかんを食べる。何かを忘れるために食べたみかん。卓上に残る寂寥感は。

これほどの極楽があろうか。体型はまさしくその人の生き方の鏡
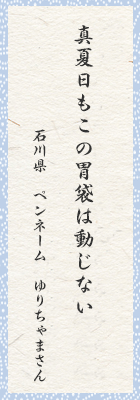
身体を鍛えるということは胃袋を鍛えるということ。鉄の胃袋が鉄の体を。
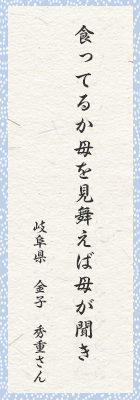
いくつになっても母は母。小さくなった母が見上げて子に言う。「食ってるか」。ドラマだ。
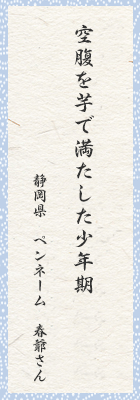
あの頃のトラウマか。今も芋とカボチャが苦手な年代。私の知人にも。

人間健康が一番の見本のような娘。時には二人三脚の主導権も奪われて。
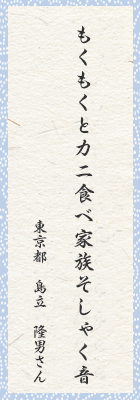
きれいとか作法とかカニを前にしては忘れるべし。この租借音が美味いの裏返し。
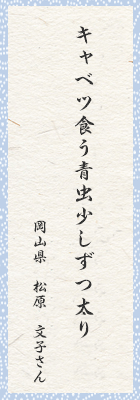
虫も食わないキャベツが旨いはずがない。キャベツが太れば青虫も。
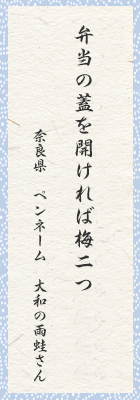
そんな時代が懐かしい。梅二つに母の愛を感じた少年期。
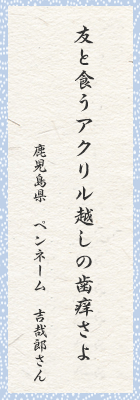
感染予防は「離れる」こと。密でいたい友を隔てる無粋に透明板。

これもまた生の厳しさ。種族を保つため生と死の「儀式」が繰り返される。

究極のSDGs。碗を省くことで「洗い」も省く。さてラーメンのお味は。
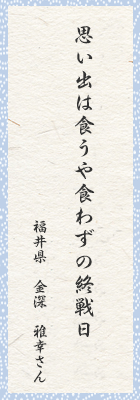
食うために生きたあの頃。タケノコ生活という言葉も生まれた。芋や野菜に化けた母の一張羅。

エンゲル係数が高い家庭では母のガマンが家族を支えた。箸に絡まぬめし粒の白。

どうしてカラスはあのように頭が良いのか。蒔いた種を証拠も残さず食べつくす。
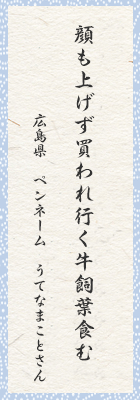
売られる朝も飼葉桶に頭を突っ込んで。酪農家はこの出会いと別れを繰り返す。
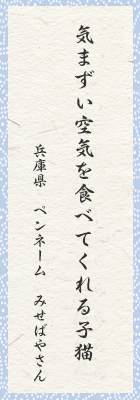
人間が解決できないことをペットの子猫が。破調だが上手い川柳作品。
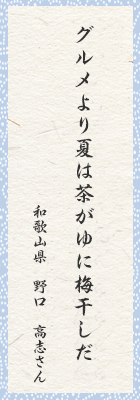
あっさりと済ませることも暑気払い。時に体が欲することも。

ようやく収穫、というトウモロコシを食われた記憶が。まさしく人の苦労を食うカラス。

食事後のスイーツ。これは一の別腹。アイスは二の別腹。若さとはかくも果てなし。
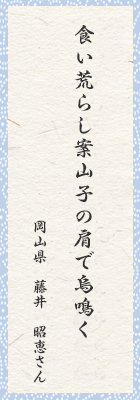
鳥とは思えない獰猛なカラス。鳥追いの案山子の肩に挑戦的な声とクチバシ。知恵者でもある。
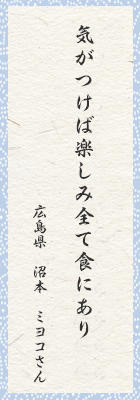
パンのみに生きる人を笑えない。血肉は食によってつくられる。

三度の飯を中心に一日を組み立てる。ひの積み重ねが一年、そして十年。
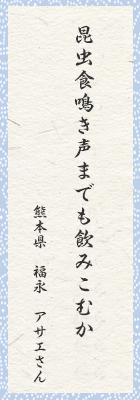
糧が危険水域。人口増と地球温暖化。キリギリスの鳴き声とどんな味だろう。

空腹時の検診。「異常ありません」の安堵感で掻き込む白い飯。
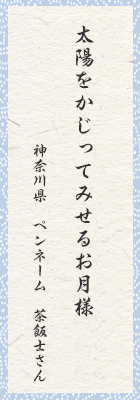
月食をこういう形で表現する人は紛れもなく詩人である。